〒142-0041 東京都品川区戸越三丁目11番12号 杉本ビル102
都営地下鉄浅草線戸越駅 徒歩5分
東京急行大井町線戸越公園駅 徒歩5分
相続、贈与及び財産評価
以下改定作業中
こちらでは相続、贈与及び財産評価について紹介いたします。
〇相続とは何のためにするのか

相続とは、日本においては、家(家族、世帯)の地位(もろもろの精神的価値、財産的権利義務)を主として世帯の主宰者であった被相続人から相続人へ承継する極めて機微に触れる財産債務の移転です。
単に物理的な財産債務の移転だけでなく、先祖代々のお墓の継承や家族の社会的名誉の継承、残された親族の世話、扶養などの継承も含まれています。
相続による財産の移転は、包括承継主義と精算主義の考え方があり、日本の相続法は基本的に包括承継主義をとっており、例外的に3か月の熟慮期間中に放棄・限定承認(精算主義はこの考え方が基本となっています。)しない限り、相続による包括的権利義務の移転を単純承認したものとされます。
このことは、極めて重要です。相続というと財産があるときに、だれがその財産を相続するかということだけが表に出てきますが、熟慮期間内に放棄、限定承認の手続きをしないと債務も相続してしまうということです。「葬式だけは出したけれど、借金があることは知らなかった。」は、理由にならないことになります。
もっとも、金融機関で住宅ローン等の借入金をするときは、生命保険に強制加入することが多いことから、その生命保険金が借入金に充当されて債務がなくなっているので表面には出てこないだけです。
テレビ番組でよくある悪質な貸金業者が、「親の借金を子供が返すのは当たり前だろ」とか「子供のしでかしたことは親が責任持つのは当然だろう」とすごむ場面は、他人ごとではないのです。
したがって、熟慮期間の3か月は短すぎるように思いますが、お解りにならないときには、なるべく早く、専門家に相談することをおすすめします。(当事務所は簡単な相談は無料ですので、是非ご利用ください。)
相続では、相続財産が金融資産だけのときは、法定相続分で遺産分割してしまえば簡単です。(後は相続税の申告が必要な時は、申告して、各自自分の相続税を支払えばいいだけです。)
ですが、被相続人の方は、どなたかご家族と一緒に住んでいらっしゃったり、どなたかのためだけの多くのお金を使ったり、財産を差し上げたりしていることが普通です。
そうすると、誰にどの財産を分けるのか以上に、
「私はこれだけのことをした」(寄与分といいます。)、
「あなたはこれだけに事をしてもらったんでしょう」(特別受益といいます。)
といった、相続人の方々の主張の調整が大切です。さらに、相続法改正により、特別の寄与が相続人以外の親族にも認められることになりましたので、この調整がうまくいかず、その後仲の良かった親族が縁切り状態になってしまうことが良くあります。(大変不幸なことです。このようなことを避けるためにも、間に入る利害関係のない調整役が必要です。是非当事務所をご利用ください。)
また、被相続人の方が個人事業を経営していたり、会社を経営(大株主の代表取締役等の役員)であったりしたときは、事業の承継が大きな問題になります。
事業の承継については、最近の税制改革を含めた中小企業の事業承継に関する法制の整備により、スムーズな事業承継の手続き整備がなされています。(事業承継これについては、当ホームページの別のページで説明しています。)
しかし、事業をしている方の周りには、ご親族を含めて、多くの様々な利害を持った方がいます。ご自分がお亡くなりになった後、いろいろな困難な問題を生じないようにするには、生前からいろいろな対策をしておく必要があります。
そこでよく言われているのは、遺言によってどの財産を誰が相続するか決めてしまうということです。また、生前贈与によりあらかじめ財産を渡してしまう方法もあります。
ただ、つまるところ「税金はいくらかかるのか」ということが大問題になります。
特に平成27年からは、相続の基礎控除が5,000万円から3,000万円に減額され、相続人一人当たりの控除が1,000万円から600万円に減額されたので、都区内に普通にご自宅をお持ちの方は、何の対策も取らなければ、相続税を支払わなければならない方が、飛躍的に増えることになります。
また、何とか、ご自分の住まいだけは遺産分割等で確保したけれど、金融資産は全部他の相続人に分割したとしたなら、大変なことになります。
ご自分の分担する相続税を支払わなければならないのです。払えなければ、結局、せっかく苦労して確保したご自宅を売った代金で支払わなければならないことになります。
さらに、何も収入を生じない不動産(別荘など)を相続した時は、少なくとも固定資産税を毎年払い続け、維持管理費を支払いつづけなければなりません。
このように遺言をするにあたっては、相続する方の財産状況のことも考えなければなりません。そのため相続税の仕組みを理解したうえで、その後の資産運用の適否まで考慮する必要があります。
どのようにすれば相続税が一番安くなるかだけを考えることなく、その後財産を相続した人がどうすればいいかを熟慮して、作成しなければなりません。
しかし、遺言ですべてが決まるかというと、そうではありません。相続人の方には遺留分というものがあります。兄弟姉妹を除いた相続人の方には、法定相続分の2分の1の金額は、必ず相続できる権利があるのです。従って、すべてが被相続人の方の思い通りになるとは限らないのです。
だからといって、生前贈与を活用しても、特別受益として遺産分割対象財産に加算されて、遺留分侵害額請求権の対象になるので、これで安心ということにはなりません。(被相続人の方が持戻し免除の意思をもって生前贈与しても同じです。)
このように相続というものをスムーズにいくように考えることは、非常に複雑で専門的な知識が要ります。目先の利益だけ考えて、損をすることはできるだけ避けたいものです。
〇贈与の活用の仕方
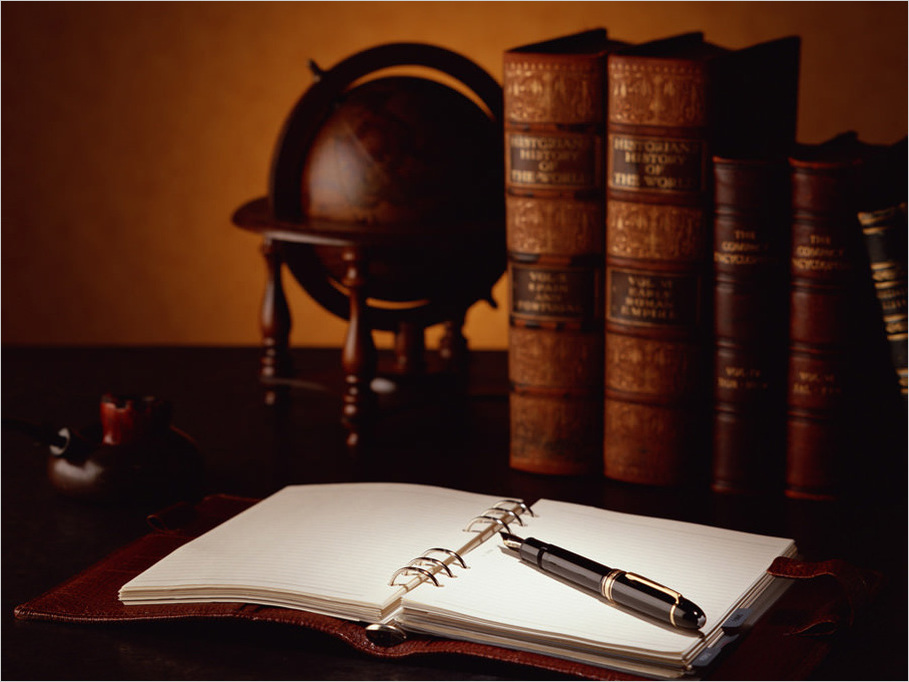
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度が大きく変わり、「結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例」、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例」が令和5年3月まで延長されましたが、
この特例措置は、「節税対策のポイント」の「結婚子育て資金の一括贈与の非課税・教育資金の非課税制度」の項目をご覧ください。
贈与税の課税方式は、暦年課税方式と相続時精算課税方式があります。暦年課税方式を原則として、相続時精算課税は、その特例として平成15年の創設されました。高齢の富裕層の資産について相続を待たずに早期にその子・孫に移転して経済を活性化させることを期待されてい
まず、注意すべきことは、特定の親族間の贈与税の課税方式を、(1)暦年課税(基礎控除=年110万円)を使うのか、(2)相続時精算課税を使うのか、ということを十分に理解する必要があります。
相続時精算課税に関しては、令和5年度の税制改正でを使うと、暦年課税の基礎控除が当該特定親族間で使うことができなくなります。
したがって、相続時精算課税選択後は、通算して2,500万円を超える贈与を特定親族から受けると、一律20%の贈与税が課されます。(相続税の前払いとして相続時の税額計算において相続税から控除されます。)
また、不動産等が価額がインフレ傾向のときは、非常に役に立ちますが、不動産等の価額が下落気味のときには、贈与した現金そのものが相続開始時に引き継がれ、相続時精算課税で取得した資産の時価が激減する(極端な話半減することもあり得ます。)
例えば住宅の建物は劣化し時価が大きく下がります。このような場合、贈与した祖父母や両親が自己資産として購入し、ご子息やお孫さんに無償で使用貸借させていたほうが、結果的に相続税評価額を下げることになります。
まして相続人と被相続人が同居している等であれば居住用の小規模宅地のの80%評価減をつかえますから、このことを知らずに、相続時精算課税を使ったら、かえって大損することになりかねないことになります。(相続時精算課税でご自分の居住用の宅地を取得した相続人に方は、居住用の小規模宅地の80%の評価減を利用できないことになりかねません。このことは、「節税対策のポイント」の「住宅資金の贈与」の項目を参考にしてください。)
受贈者のお子様が先に亡くなって、両親が相続することもあり得ます。
また、贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上で居住用不動産を取得するためのものなので、夫婦が同居する不動産を対象とすることになります。
ほかに賃貸用の貸しビル等をたくさん持っている大資産家の方なら別ですが、上述のように居住用財産の80%の評価減と相続税の配偶者の税額軽減(1億6千万円)を使えば、たいていの場合は、相続税がかからなくなり、相続のときにはかからない贈与による不動産取得税や高い税率の登録免許税を支払わなければならないことになり、確実に損をします。
以上のように、相続税対策で贈与税の特例を安易に使うと、馬鹿を見ることになります。
結局、贈与の暦年課税制度の基礎控除110万円をコツコツ活用するのが一番無難かと思います。ただこの際も贈与額は120万円として毎年贈与の申告により1万円づつの贈与税を払うことをおすすめします。
申告することなく数十年たった時に、相当額の財産移転があり、相続財産逃れではないことの証明には、贈与税の申告を継続することが手っ取り早いからです。
もっと多額の財産を移転したいなら、贈与税の最低税率10%の税率の上限と基礎控除の合計の310万円を毎年贈与し、毎年20万円の贈与税を支払えば、贈与税差引後10年で2,900万円、20年で5,800万円の財産を移転できます。
20年で400万円の贈与税が、高いと思うか安いと思うかは、相続税の前払いを一番安い税率で納付したと思えばどうでしょうか。
もっともこれは多額の財産をお持ちの方の話なので、私たち庶民には関係のない話かもしれませんが?
〇財産評価とは

財産が、全部現金と預貯金なら評価はいりませんので、とても楽なのですが、実際にはご自宅の土地建物等の不動産、投資した株式、債券、書画骨とう品、経営している会社の資産等、様々です。
建物は固定資産税評価額、上場株式は相続時の株価でいいので比較的楽ですが、土地については有名な路線価があるからそれに面積をかけるだけなので簡単じゃないかというと、そうではありません。
土地の評価は、土地の所在場所や形状により、奥行補正、側方加算、間口狭小補正、不整形補正等の修正計算を行い、土地の中に道路のセットバックとか隅切りがあって評価できないときの評価の見直し等、とてもややこしいものです。
また、上記で説明しましたが、相続人の居住用宅地の相続については一定の場合に80%の評価減が認められ、事業用宅地も一定の場合に80%の評価減、不動産貸付用の宅地の50%評価減(貸家建付地の借家権対応の評価減後の価額)のもあります。(これらを総称して、小規模宅地等の課税の特例といいます。)
平成25年の税制改正で、相続税の基礎控除が減額されたのに対応して、小規模宅地の適用面積が、居住用宅地の場合は240㎡から330㎡に、事業用400㎡と不動産貸付用200㎡は変わりませんが、居住用宅地と事業用宅地の完全併用が認められ、この二つで730㎡までが80%減の対象となりました。
ただし、奇異なのは、不動産貸付用が絡むと、最大400㎡だったものが減少させられてしまうのです。結局不動産貸付用の50%減は、使うのが難しいことになっています。(一番ベストな組み合わせを考えることになります。)
経営している会社の評価(非上場株式の評価)は、きわめて複雑です。数ある税法の中で、一番ややこしい規定です。
まず、会社の規模や同族株主の議決権の割合で評価方式が原則評価方式、配当還元方式に区分され、原則的評価方式は、業種、売上金額、資産金額、従業員数によって大・中・小の会社に分類され、中会社はさらに3段階に区分のうえ、類似業種比準方式、純資産価額方式、(S1+S2)方式、(類似×0.25+純資産×0.75)方式という複雑な計算式の評価方法に分けられ、さらに種類株式の権利の内容によっても違ってきます。
このほかの財産も、その種類に従った評価が必要です。
このように財産の評価は複雑怪奇なので、専門家に任せたほうが賢明です。
相続があったときの手順
相続発生前にやっておくこと
相続対策において、何よりも大事なのは「争族防止」で、その次は「納税資金対策」です。「節税」は、この二つの優先事項をクリアする過程のアイテムの一つと考えて下さい。
ある程度資産をお持ちの方は、何らかの資産管理をしていらっしゃいますが、全体像を把握していらっしゃる方は少ないと思います。
まず、資産の種類と金額債務の額を整理し、ご自分の財産の棚卸をしてみましょう。(財産目録のほか、貸借対照表を作りましょう)。
特に債務にはどんなものがあるかを調べておき、債務を相続人に方に負わせることを避けるため、返済資金・返済方法も考えておいてください。
その後で、遺産を相続人等のどなたに引き継いだらよいかを考えてください。(場合によっては生前贈与も有効ですし、遺言によって、あらかじめ相続人を指定することも可能です。)
お亡くなりになる直前にやらなければならないこと
被相続人の方が、お亡くなりになると、預貯金その他の金融資産は、金融機関で凍結されてしまします。
そのため、病気が重く、重体な時などには、相続人の方が、ある程度の当面必要な現金を引き出しておくことが必要です。(銀行によっては、医療費の請求書、葬儀関係費用の請求書等で相続人全員で支払わなければならないものは、振込みもしくは引出を認められる場合もあります。)
あとは、親族の皆さんが落ち着いて、心安らかなな最期を看取って差し上げてください。
葬儀が終了し、落ち着いたら、やるべきことを整理しましょう
お亡くなりになられた後は、死亡届の手配、ご葬儀の手配のほか、ご高齢のときは公的年金の手続、健康保険の手続等、すべきことがたくさんあります。葬儀の終了後は、なかなか次のことを考える余裕がないと思いますが、早く気持ちを落ち着けて、これからすべきことを考え、整理しましょう。
相続関係の諸手続きには期限があります。
相続放棄・限定承認3か月、
準確定申告4か月、
経営承継相続人の代表権取得期限5か月、
根抵当権の合意の登記6か月、
経済産業大臣の認定申請8か月、
相続税申告10か月等
被相続人の事業を継続する方がいるときは、次のことに注意しましょう。
事業を承継した方の青色申告承認申請は、相続が8月までなら、相続の日から4か月以内、9月及び10月なら12月まで、11月及び12月なら翌年の2月15日までに、申請書を提出する必要があります。
また消費税の簡易課税の課税事業者を相続で承継したときは、相続した課税期間の終了(原則12月末日)までに、事業を承継した相続人が簡易課税の選択届を提出する必要があります。
遺言はありますか、遺産の全部を調べましょう
被相続人の方の遺言は、財産の承継に当たり最優先に扱われます。遺言がある場合は、公正証書遺言以外の遺言書は開封する前に、家庭裁判所の検認が必要です。遺言があってもなくても、遺産の全部を調べてください。また、生前贈与の有無、その内容を確認してください。
事業の継続はどうしますか、各種許認可、届出の変更が必要です
遺産の全部が確認できたら、相続人全員で、遺言の内容を確認し、もしくは事業の継承者を決め、遺産分割の概要について、意見をまとめておきます。事業の継承者が決まっているときは、なるべく早めに関係機関等に変更等の手続きをしてください。
所得税の準確定申告をしましょう
被相続人の方の所得税と消費税の申告期限までに、準確定申告をすることが必要です。
相続税の仮計算をしましょう
すべての相続人が判明し、全員の意見を調整して、相続財産を仮に相続人に分配して、相続税の仮計算をします。各相続人の負担する相続税、相続債務、節税対策を参考に具体的相続分を再調整します。(各相続人の納税資金、返済資金の有無はこの段階で必ず検討しておいたほうが無難です。)
この際調整は、相続人の方が全員納得できるよう何度でも調整します。(相続期限に間に合わないときは、2か月の申告期限の延長ができます。)
遺産分割協議書を作成しましょう
相続人全員による遺産分割の合意が得られたら、すぐの遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名、実印による押印をし、全員から印鑑証明書、住民票、戸籍謄本等の必要書類を提出してもらいます。
相続税の節税対策等に必要な登記等を済ませましょう
遺産分割により各相続人に承継された財産のうち、例えば小規模宅地の特例等、移転登記が適用要件とされているものは相続税の申告に先立って、所有権移転登記をします。各種の納税猶予の特例も、登記や許認可、届け出等を要件としている場合は、同様に相続税の申告前に手続します。
相続税の申告をしましょう
STEP9までの手続きが、完全に終わったら、相続税の申告書を作成し、申告します。同時に各種納税猶予等の届けも提出します。
評価額を下げることのできる財産とできない財産
作成中
1 相続税、贈与税の財産評価の仕組み
相続税法では、第3章の財産評価
その他のページのご案内
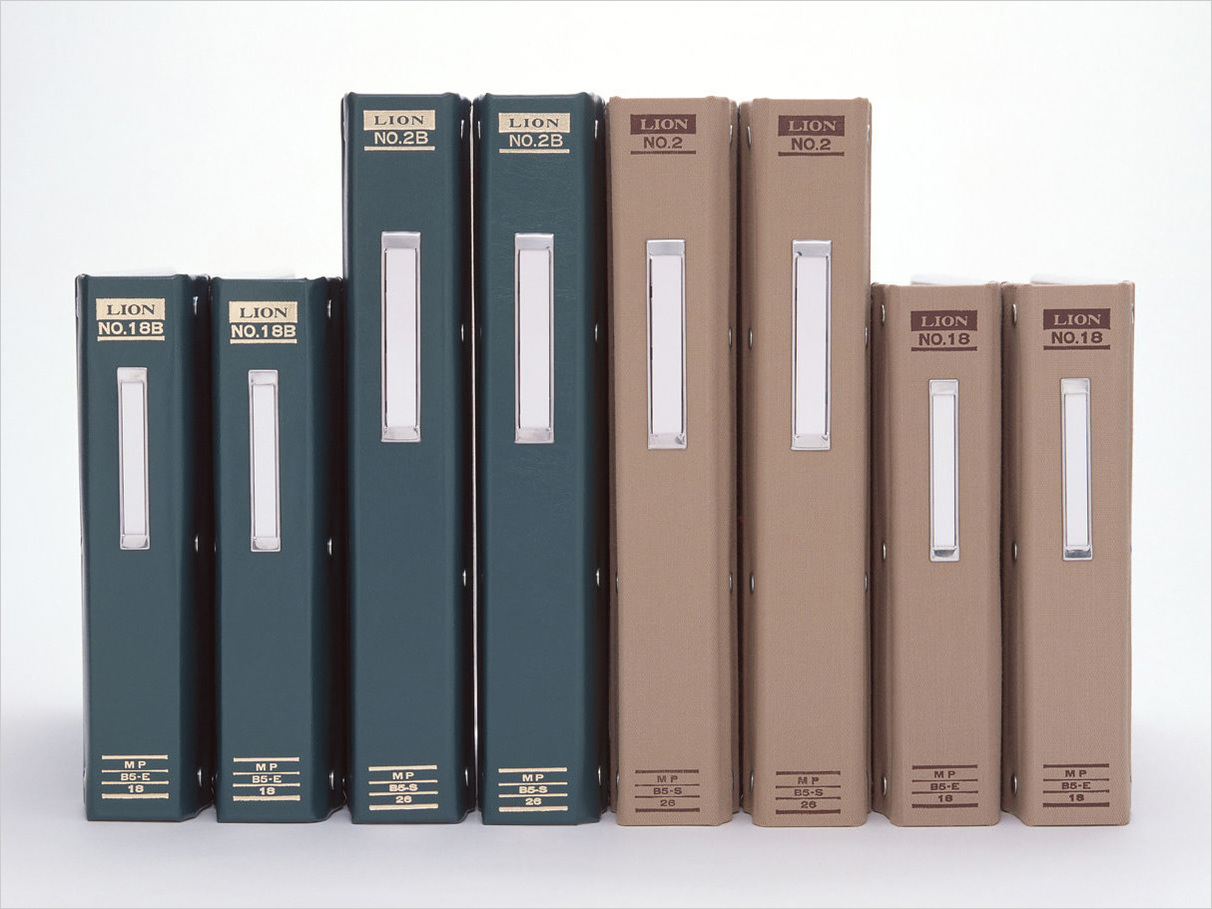
事業をするのに必要な許認可についてご案内しております。
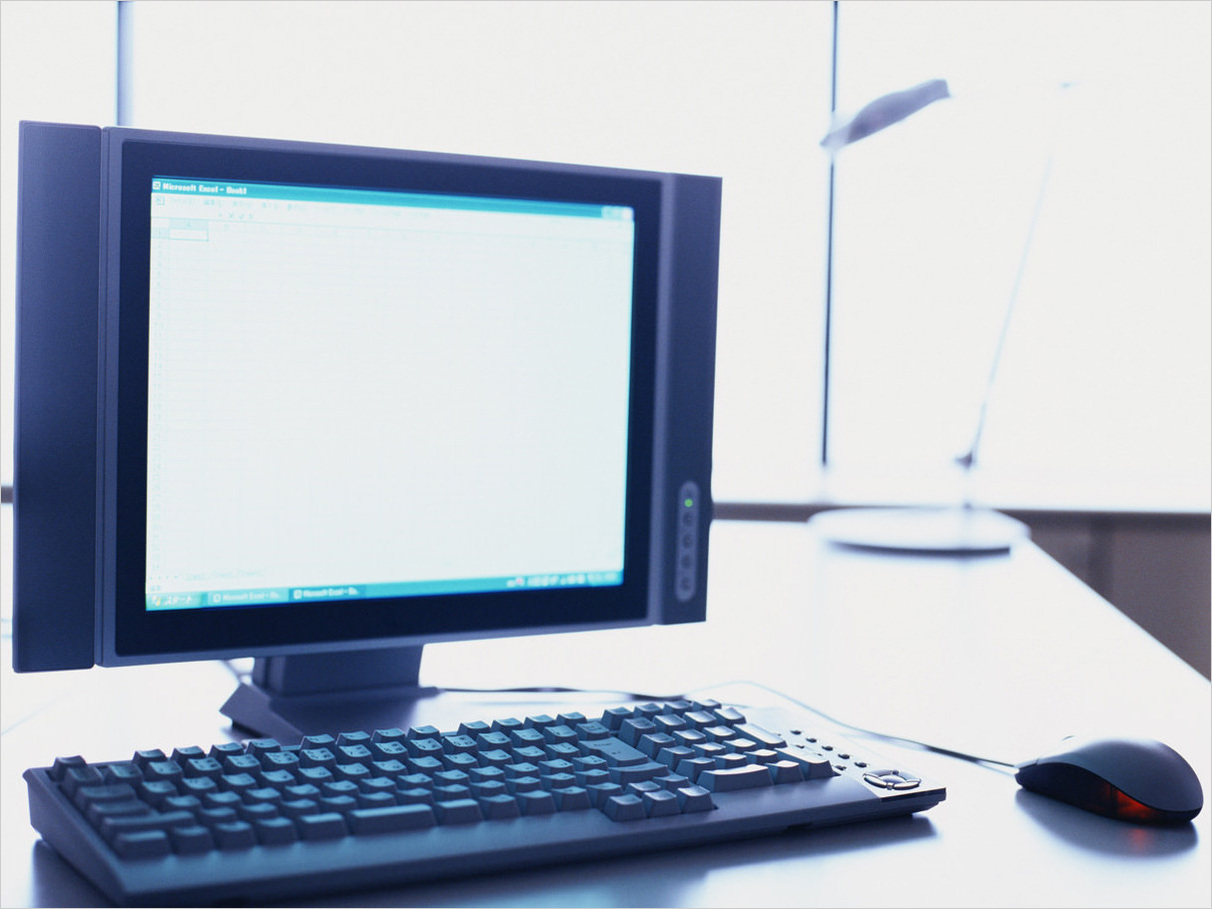
税務調査とその対応についてご案内しております。

事業承継についてご案内しております。

お問合せ・ご相談はこちら
担当:杉本(すぎもと)
いつでもお電話ください
※来所でのご相談の場合は、事前にご連絡ください
東京都品川区戸越の杉本総合事務所です。品川区、目黒区、大田区を中心とした城南地区で,税理士及び行政書士の総合経営法務サービスを皆様にお届けいたします。
個人の方の事業の各種許認可から帳簿の記帳、決算,確定申告まで、また、法人の場合は設立から各種許認可、帳簿の記帳、給与計算、決算、確定申告、さらに、事業承継、相続までの一連のサービスをお届けするため、一生懸命汗をかいて、みなさまのお役に立ちたいと思います。
| 対応エリア | 東京都区内(特に品川区、大田区、目黒区を中心とした城南地区) |
|---|
お役立ち情報
サービス案内
事務所紹介
主な業務地域
東京都区内(特に品川区、大田区、目黒区を中心とした城南地区)

